12 アリスがわけを語る

「ここです!」と声を上げるアリス、とっさのことであたふた、この数分で自分の図体がどれだけでっかく育っていたかどわすれしちゃっててね、あんまりあわてて立ち上がったものだから、スカートのすそがひっかかっちゃって裁判員のいる箱形の座席ざせきが横転おうてん、裁判員全員が下でおさばきを聞いているひとたちの頭上にすってんころりん、そのときのみんなは手足をじたばたさせていたので、思わず先週うっかりひっくりかえした金魚ばちのことがものすごく重なってね。
「あら、ごめんあそばせ!」と口をついて出るもののどうにもあたふた、大急ぎでひろい上げはじめてね、だって金魚でのうっかりがずっと頭にあったから、なんとなくそう思えたんだ、すぐにひろい集めて座席にもどさないと死んじゃうって。
「おさばきが進められんな。」と言うキングの声はものものしい、「裁判員みなをおのおのの持ち場にちゃあんともどすまで――みなをな。」と最後のところを力強くねんおししつつ、アリスをじろり。
アリスが座席に目をやると、見えたのは、あわてていたからか、頭から逆さかさにつきささったトカゲ、このかわいそうなやつは、しおしおとしっぽをふりふり、身動きがまったく取れてなくって。もう1度ぬき出してからちゃんと入れ直す。「さして大した差でもないのに。」とひとりごと。「たぶんそもそもおさばきの役に立ちようがないし、どっちが上でも。」
ひっくり返されたどきどきからいささか立ち直った裁判員一同、見つかった手持ち黒板とチョークを手元に置いたとたん、せっせと仕事に取りかかってね、みんなしてこの事故じこのいきさつを書き出したんだけど、トカゲだけは別、すっかり参ってしまったのか、できることといえば、こしを下ろして口をあんぐり、おさばきの場の天井をぼんやり見上げるばかり。
「事と次第について何を知っておる?」とキングからアリスへ。
「なんっにも。」とアリス。
「これっぽちもないか?」としつこいキング。
「これっぽちも。」とアリス。
「なんとよしありげな。」とキングは裁判員へと顔を向けてね。みんなそのことを黒板に書き出したところへ、白ウサギが口をはさむ。「よしなし、とのつもりでおじゃりましたか。」と言葉こそうやうやしいけど、話すあいだもみけんにしわでしかめっ面。
「よしなし、とのつもりであったぞよ。」とあわてて口にするキング、ぼそぼそと続けるひとりごと、「よしあり――よしなし――よしなし――よしあり……」どっちが聞こえがいいのか品定めしてるみたいに。
裁判員には「よしあり」と書きとめた者もあれば「よしなし」とした者もいて。かろうじて黒板をのぞけるところにいたアリスは、これを見て、「どのみち大差なくてよ。」とひとり思う。
このときのキング、しばらくいそいそと手元のメモに何かをしたためてたんだけど、いきなり声を出してね、「静まれ!」って、それからそのメモを読み上げたんだ、「決まりその42。『背たけが1.6キロをこえた者は何ぴともおさばきから退場たいじょうとする。』」
みんながアリスに目をやる。
「あたくし、1.6キロもなくってよ。」とアリス。
「ある。」とキング。
「3キロ近くはある。」と後おしするクイーン。
「ふん、出て行かないもん、ぜったい。」とアリス。「それにちゃんとした決まりでなくてよ。たった今でっち上げたんだから。」
「ここに記されたものでもいちばん古い決まりじゃ。」とキング。
「なら、決まりその1のはずじゃなくって。」とアリス。
顔を青くしたキングは、あわててメモ帳をとじる。「では、おさばきを話し合え。」とふるふる小声で裁判員に。
「まだまだやることがおじゃりまする、キングさま。」と白ウサギはとび上がって大あわて。「このような紙が今しがたとどいておじゃります。」
「中には何と?」とクイーン。
「まだ開けておじゃりませんが、」と白ウサギ、「おそらくは手紙かと、とがびとの手になる――だれかしらあての。」
「そうにちがいなかろう、」とキング、「あて名がないのでないかぎりは。まあまずあるがな、ほれ。」
「だれにあてたものなんです?」と裁判員のひとり。
「あて先が何もないでおじゃる。」と白ウサギ。「むしろ、そとみには字は何もおじゃりません。」と言いながら紙を広げると言葉をついで、「つまるところ手紙でないでおじゃる、これはひと続きのポエム。」
「字の書き方はとがびとのものですか?」と裁判員がもうひとり。
「いえ、ちがうでおじゃる、」と白ウサギ、「そこがたいそうけったいで。」(裁判員はみなハテナだらけのお顔。)
「だれかしらの字の書き方をまねたにちがいない。」とキング。(裁判員みな顔がまたぱっと明るくなる。)
「申し上げます、キングさま、」とジャック、「わたくしめは書いてません、そうだと言い切れるだけのものもないでしょう? 終わりに名前もそえられてないんですから。」
「名前がないならば、」とキング、「よけいに事はまずくなるぞよ。つまりおぬしはお痛いたをしたことになる。でなければ、いい子としてちゃんと自分の名をそえるはずだからな。」
これにはその場一同の手からぱちぱちぱち、キングがこの日初めてほんとにうまいことを言ったもんでね。
「はっきりした、やったのはおまえぞ、もちろん。」とクイーン。「では首をちょ……」
「そんなの何もはっきりしてなくってよ!」とアリス。「ふん、何が書かれてあるかもわかってないのに!」
「読み上げよ。」とキング。
白ウサギはメガネをかけてね。「キングさま、どこからお始めに?」とたずねる。
「はじめから始めよ。」とのべるキングはものものしい。「そして続けて、とうとう終わりに来たら、そこでやめよ。」
静まりかえるおさばきの場、そのなかで白ウサギが読み上げたのは次のポエム――
あいつらの話じゃ あの女のところで
おれのことを あの男にしゃべったそうだな
あの女はおれを いいやつと言ったが
おれは泳げないと 言いくさる
あの男があいつらに、 おまえはでかけて
ないと伝えたぞ(おれたちにもたしかなことだ)
あの女がことを おし進めたら
おまえはいったい どうなるやら
おれ→あの女は1 やつら→あの男は2
おまえ→おれたちは3 いやもっとだ
あいつらみんなもどる あの男→おれへ
もともとそいつらは おれのものだったがな
まんがいち おれとあの女が
この件けんに まきこまれでもしたら
あの男はおまえに やつらのあつかいをまかす
おれたちのときと まったく同じだ
おれが思うに それまでおまえは
(あの女が かっかするまでは)
出しゃばって じゃまするつもりだったんだろ
あの男と おれらとそれのあいだを
あの男にはもらすなよ あの女の1番びいきが
あいつらだって だってそりゃあ
ひみつに決まってる だれにも言うなよ
おまえとおれ ふたりだけのないしょだ
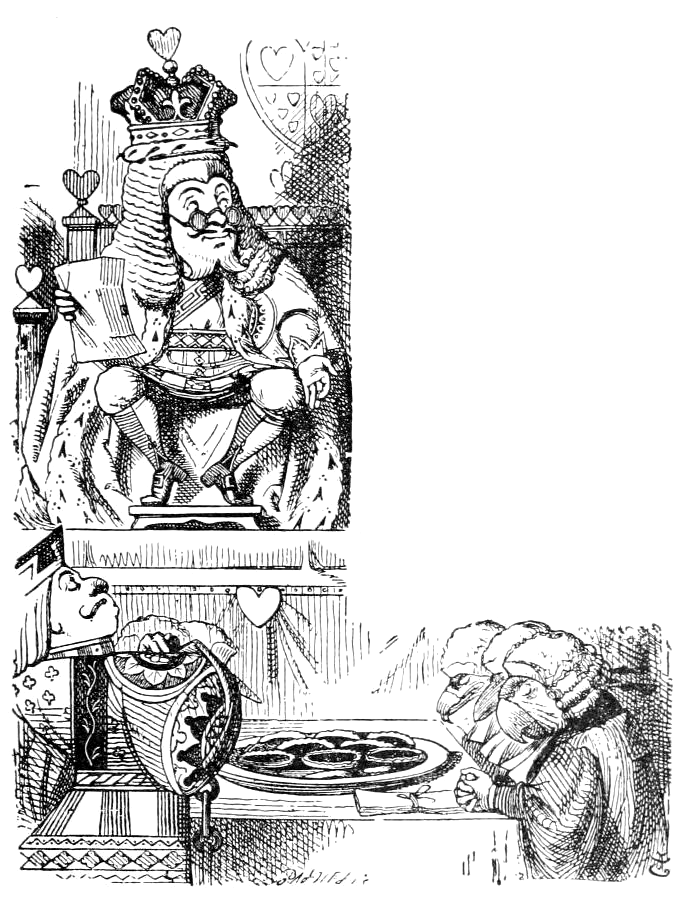
「今まで聞いたなかでも、いちばんのよしありげなわけじゃぞ。」とキングは手をもみもみ、「では今こそ裁判員よ……」
「そこのだれかがこのポエムを読みとけたら、」とアリス(このほんの数分でたいへん大きくなっていたので、まったく物おじもせず口をはさんでね)、「銀貨ぎんか1まいあげてもよくてよ。こんなのこれっぽちの意味もないと思うけれど。」
裁判員もみんな手持ちの黒板に書きとめてね、「こんなのこれっぽちの意味もないと思うと女。」ところがそのうちのだれもその紙を読みとこうとはしない。
「もし意味がないのだとすれば、」とキング、「すさまじく手間がはぶけるぞ、ほれ、何も探らんでよくなるからの。とはいえどうなのかの。」と続けて、ひざ上にそのポエムを広げ、片目でじっと見てみるも、「どうにも何かしらの意味はありそうじゃ、やはり。『……おれは泳げないと言いくさる……』おまえは泳げないのだったな。」と言葉をついで、ジャックに顔を向ける。
ジャックは悲しげにかぶりをふって。「見ての通りですよ。」と返事。(たしかにできそうにない、まったくの厚紙あつがみだからね。)
「ここまではよろしい。」とキング、そしてひとりごとみたくぶつぶつそのポエムを読んでいく。「『おれたちにもたしかなことだ』――これはもちろん裁判員のことじゃな――『あの女がことをおし進めたら』――これはクイーンのことにちがいない――『おまえはいったいどうなるやら』――おお、まったくだ!――『おれ→あの女は1 やつら→あの男は2』――ほほう、こうしてやつはパイをよろしくしたわけか、ほれ……」
「でも続きに『あいつらみんなもどる あの男→おれへ』って。」とアリス。
「うむ、だからそこにある!」とキングはしたり顔でテーブルのタルトを指さす。「これほど明らかなことはないとも。そののちまた――『あの女がかっかするまでは』――おまえや、かっかしたことなどないじゃろ?」と言葉をクイーンへ向ける。
「ない!」と言いながらもクイーンはとちくるってインクびんをトカゲに投げつけてね。(とんだ目にあったビルくん、黒板から指で書くのをやめていてね、何も書けないと気づいたからなんだけど、でもこうなってあわててまた取りかかって、顔からしたたるインクを使ってとうとう使い切った。)
「まあ『かっか』というよりは『へいか』じゃしのう。」とキングはおさばきの場を見回しつつ、にやり。あたりは死んだようにしーん。
「だじゃれじゃ!」と続けてキングはむすっとすると、みんな大笑い。
「さて裁判員よ、おさばきの話し合いだ。」とキングは言うんだけど、これこの日でもう20回目くらいにはなるかな。
「いいえっ!」とクイーン、「言いわたすのが先――話し合いは後あと!」
「がらくたのすっからかん!」とアリスの大声、「言いわたすのが先だなんて!」
「だまらっしゃい!」と血相けっそうを変えるクイーン。
「だまらない!」とアリス。
「このむすめの首をちょん切れ!」とクイーンがありったけの裏声をはる。ひとりも動かない。
「だれが言うこと聞いて?」とアリス(このときまでに元々の背たけになっていてね)。「あんたたちみたいなただのトランプ!」

せつな、トランプがいっせいにおどり上がり、空からふりそそいでくる。きゃッと、びくつき半分、むかつき半分で打ちはらおうとしたら、気づけばもとの木かげ、お姉さまにひざまくら、木から頭にひらひら落ちかかっていたかれ葉をやさしく取りはらってくれていて。
「起きて、アリスちゃん。」とお姉さま、「もう、長々としたお昼ねだこと。」
「ねえ、あたくしもう、へんってこなゆめ見てたの!」とアリスはお姉さまに自分がおぼえているかぎりのことを、自分のとっぴなめぐり歩きを、ここまで読んできた通りぜんぶおしゃべり、終わるとお姉さまはキスをしてくれてね、こう言うんだ。「へんてこなゆめだったのね、ほんと。でもすぐにお茶へかけ足しないと、このままだとちこくよ。」というわけで、アリスは起き上がってかけ足、走りながら心のなかは、そりゃやっぱり、これまでのふしぎなゆめのことでいっぱい。
ところがお姉さまは妹がはなれていったあともじっとすわったまま、ほおづえをついて夕ぐれをながめながら、小さなアリスとふしぎめぐりの道行きを考えているうち、今度は自分もうつらうつらゆめを見始めてね、そのゆめっていうのはこう――
はじめにゆめ見るのは、その小さなアリスのこと。何度となく小さなお手々をこちらのひざの上でにぎりながら、さらにきらきらわくわく上目づかいでのぞきこんでくる――聞こえるのはあのいつもの声音、目に入るのは頭をつんと上げるあのけったいなくせ、いつも毛がちらかってどうしても目に入ってしまうからってそうやって元にもどそうとするんだ――そしてじっと耳をかたむける、たぶんかたむけるうちに、そのまわりのあちこちが、小さな妹のゆめのなかのとっぴな生き物でにぎやかになってくる。
長い草が足下でがさごそ、白ウサギがあわててかけてゆく――びくびくネズミがばしゃばしゃ、そばの池を進んでいて――聞こえてくるティーカップのかちゃかちゃ、ヤヨイウサギとなかまたちは、いっしょにいつまでも終わらないお茶会中、そのあとクイーンがきぃきぃ声でかわいそうに来たひとみんなを処すとか言いだして――またもやブタの赤ちゃんが御前さまのおひざでくしゅん、そこへ大皿小皿ががちゃんばりん――ふたたびグリフォンの鳴き声、トカゲの黒板チョークのきーきー、さらに取りおさえられたモルモットのもがく声があたりにひびき、そこへかなたからまじり合うあわれなウミガメフーミのさめざめ。
だからじっとしたまま、ひとみをとじていると、もう半なかばふしぎの国にいるようで、目をいまひとたび開けてしまえば、つまらない現実うつつにみんな変わってしまうとわかっているのに――草はきっと風でかさかさしてるだけで、池がそよぐ草に波を立てているだけで――ティーカップのかちゃかちゃは羊につけられた鈴の音に、クイーンのきぃきぃ声も羊かいの男の子のさけび声に――さらに赤ちゃんのくしゃみ、グリフォンの鳴き声、そのほかけったいな物音だってみんな(わかってる)、きっとせわしない牧場まきばのごちゃごちゃがやがやに――それから、遠くから聞こえる牛のモーモーに、ウミガメフーミのなみだ声も入れ変わってしまうだけなのに。
最後にひとり思いえがくのは、この当の小さい妹がこれから先、ひとりの女に育っていくさま。大人にふくらんでいくなかでもずっと、子どものころの、すなおなあたたかい心を持ち続けていくのか。そして、だれかの子どもをそばに集め、たくさんとっぴな話をしては、その子たちの目をきらきらかがやかせるのだろうか。その話は、遠い昔のふしぎの国のゆめそのものだったり? すなおに悲しむその子たちのそばで、自分もと、すなおにはしゃぐその子たちにかこまれ、楽しかったと気づくのかな、自分の子ども時代の思い出、あの幸せな夏の日々に。
